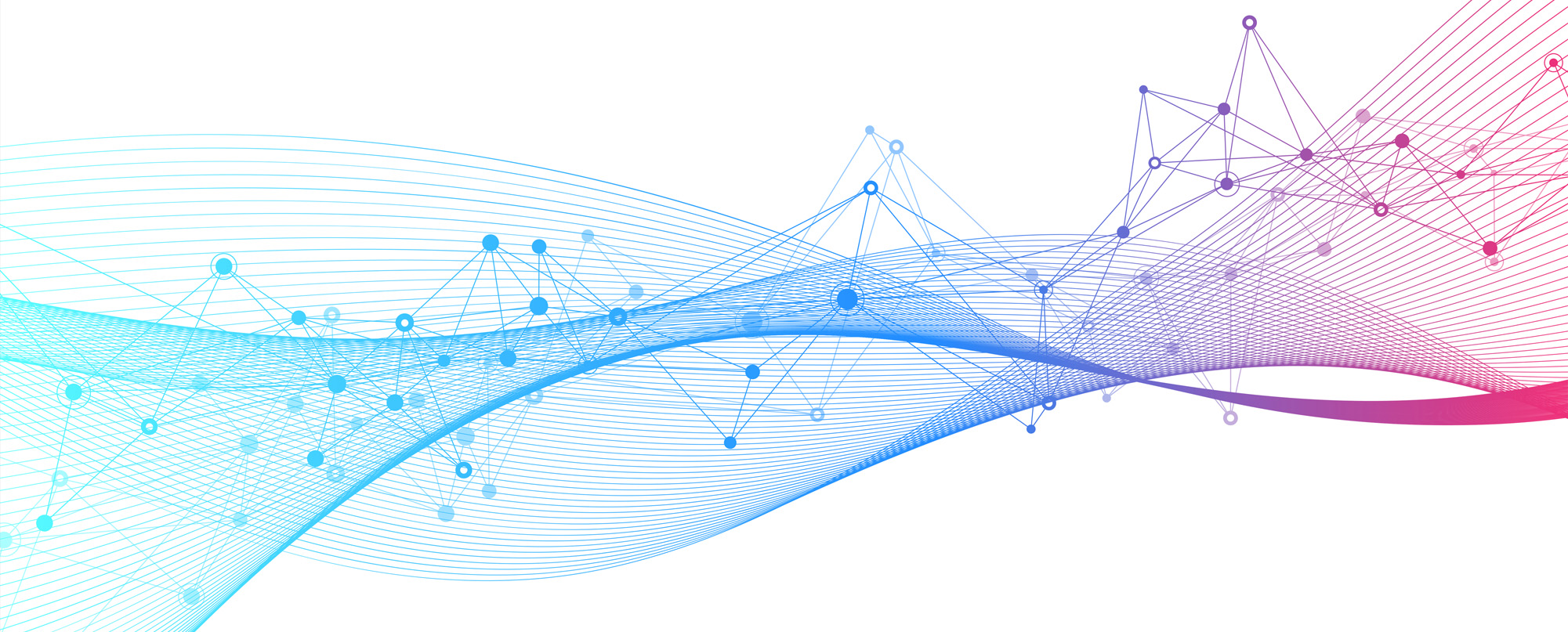| 年月 | 主な出来事・活動内容 |
|---|---|
| 2017年10月 | 「超早産児神経発達症研究会」として発足。早産児、特に在胎28週未満の超早産児の神経発達に関する研究と支援の必要性を啓発し、専門家・医療従事者・教育・福祉関係者のネットワークづくりを開始。 |
| 2018年〜2019年 | 学術・社会活動を拡大。研究会形式でのセミナー・研究報告会を定期的に開催し、早産児の発達予後、支援の実践例、保護者支援の方法などをテーマとした議論を重ねる。 |
| 2020年 | COVID-19パンデミックの影響を受け、一部活動をオンライン形式に移行。オンデマンド配信やウェビナー等を通じて、遠隔地の参加者や多様な専門分野からのアクセスを拡充。 |
| 2021年 | 研究発表・成果の共有を強化。国内外の学会・ジャーナルとの連携を進め、早産児神経発達に関する最新の科学的知見の紹介と共有を促進。保護者ワークショップや教育・福祉機関との協力を拡大。 |
| 2022年 | 年次セミナーの開催等を通じて、早産児の神経発達症の早期発見・早期支援の重要性を広く啓発。政策提言・医療・教育分野でのガイドライン作成に向けた議論を開始。 |
| 2023年 | 年度セミナーを含む研究会報告を実施。具体的な研究成果の公表、また臨床現場での支援体制のモデル事例の提示。動画配信や資料ダウンロード機能を充実させ、会員・研究者・関係者がより使いやすい情報基盤を整備。 |
| 2024年 | 教育現場・社会福祉機関との連携をさらに強化。早産児の発達特性に関する理解を深めるための普及活動、保護者支援プログラムの開発・試行を実施。研究奨励/助成制度の検討を始める。 |
| 2025年6月 | 学会名称を「早産児神経発達学会」に改称。超早産児の神経発達研究と支援を一層推進するため、新たな章(ステージ)へと歩みを進める。今後は医学的・教育的・社会的支援の統合、早期診断・介入の促進、家族への包括的支援体制の構築を重点課題とする。 |
過去に開催した研究会
第1回 2017.10.13(埼玉) 発起集会

第2回 2018.2.10(神戸)
<演者>
久保健一郎(慶應義塾大学)、城所博之(名古屋大学)、藤岡一路(神戸大学)、福井美保(大阪医科大学)、竹内章人(岡山医療センター)、荒井 洋(ボバース記念病院)

第3回 2018.11.23(東京)
<演者>
竹内章人(岡山医療センター)、高橋立子(五十嵐小児科)、城所博之(名古屋大学)、久保健一郎(慶應義塾大学)

第4回 2019.6.2(名古屋)
<演者>
城所博之(名古屋大学)、出口貴美子(慶應義塾大学)、久保健一郎(慶應義塾大学)

第5回 2019.09.29(東京)
<演者>
城所博之(名古屋大学)、出口貴美子(慶應義塾大学)、久保健一郎(慶應義塾大学)

第6回 2019.11.27(鹿児島)
<演者>
辻雅弘(京都女子大学)、福井美保(大阪医科大学)、前田剛志(大垣市民病院)、城所博之(名古屋大学)

第7回 2020.8.2(Zoom)
<演者>
北井征宏(ボバース記念病院)、久保健一郎(慶應義塾大学)、竹内章人(岡山医療センター)、伊藤裕史(青い鳥医療療育センター)、佐藤義朗(名古屋大学)

第8回 2020.11.15(Zoom)
<演者>
森岡一朗(日本大学)、向井丈雄(東京大学)

第9回 2021.2.7(Zoom)
<演者>
山口真美(中央大学)、永田雅子(名古屋大学)

第10回 2021.(Zoom)
<演者>
岩永竜一郎(長崎大学)、福井美保(大阪医科大学)

第11回 2021.6.13(Zoom)
<演者>
加納有規(超早産児の父)、小野田淳人(山口東京理科大学)

第12回 2021.10.17(Zoom)
<演者・タイトル>
小松光友(ボバース記念病院)『超早産児の発達と支援』
荒井洋(ボバース記念病院)『超早産児の両側線条体萎縮の臨床像』
荒田晶子(兵庫医科大学)『自発性活動の胎生期〜新生児期における役割』

第13回 2022.3.27(Zoom)
<演者・タイトル>
藤原加奈江(東北文化学園大学)『乳幼児期の記憶をもつ自閉症者の神経心理学』
今福理博(武蔵野大学)『早産児の認知機能と言語発達』
.png)