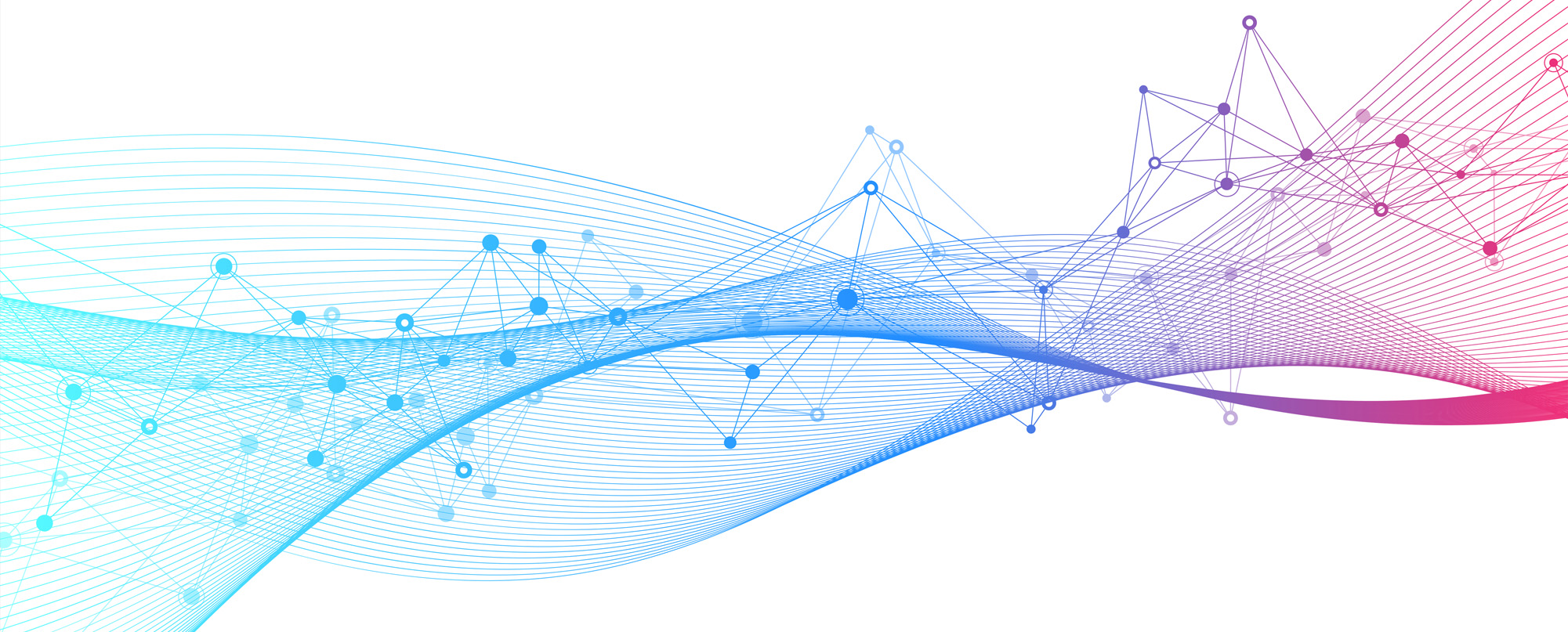私たちは、2017年10月13日に「超早産児神経発達症研究会」として発足しました。
その後、学術的・社会的活動を継続してきた中で、早産児の神経発達に関する研究と支援の重要性が一層高まったことを受け、2025年6月より『早産児神経発達学会』として新たな歩みを始めました。
早産児、特に在胎28週未満の超早産児においては、医療の進歩により生存率が大きく向上した一方で、その後の神経発達における課題が注目されるようになってきました。かつては脳室周囲白質軟化症(PVL)などの白質病変に伴う脳性麻痺が大きなテーマでしたが、近年では、自閉スペクトラム症や注意欠如多動症などの神経発達症の傾向が、より重要な課題として浮かび上がっています。
これらの発達特性は、乳児期には表面化しにくく、運動面で目立つ障害がない限り、早期の療育や支援に結びつきにくいという現状があります。その結果、学童期に入ってから学習困難や社会的な適応のしづらさとして顕在化し、臨機応変な対応が苦手で恥ずかしがり屋といった性格傾向も相まって、心理的な困難を内に抱える子どもが多くいることがわかってきました。さらに成人期には、精神疾患のリスクが高く、経済的にも平均所得が低い傾向があるなど、ライフステージを通じた継続的な支援の必要性が明らかになっています。
このような背景を受けて、本学会では、早産児の神経発達に関する神経科学的な研究を進めるとともに、早期診断と介入の可能性を探り、医学的・教育的・社会的な支援体制の整備に取り組んでいます。子どもたちの脳機能の理解を深め、その臨床像を明らかにし、さらに家族へのサポートも含めた包括的な支援体制を構築していくことを目的に、医療・教育・福祉の各分野が連携しながら活動を続けています。
私たちは、科学的根拠に基づいた実践と、子どもたちやその家族の人生に寄り添う姿勢の両立を目指し、今後も研究と実践を推進してまいります。より多くの方々にこの取り組みに関心を持っていただき、ご参加いただけることを心より願っております。
本学会の学術的・社会的な活動をより一層推進していくためにも、多くの皆さまのご参加と温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。



.png)