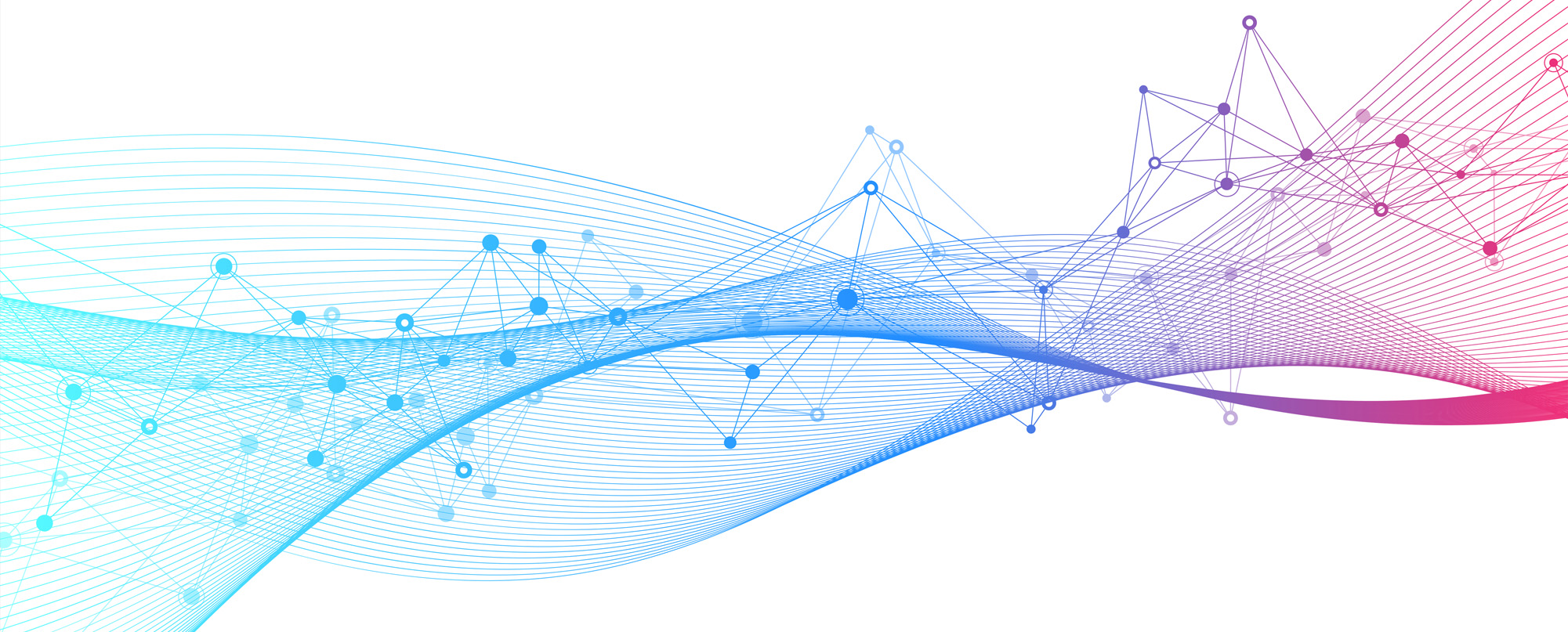代表理事 出口貴美子

キッズ&ファミリークリニック 出口小児科医院 院長
一般社団法人 早産児神経発達学会 代表理事
認定NPO法人 Love&Safetyおおむら 代表理事
CCC(福島の子どもと保護者のこころのケア団体) 代表
日本救急医療教育機構(心肺蘇生教育)トレーニングサイトコーディネーター
2025年6月2日、「一般社団法人 早産児神経発達学会」を設立し、初代理事長を務めさせていただくことになりました出口貴美子と申します。
近年、周産期医療と科学の進歩により、早産児の予後は大きく変化してきました。1962年に脳室周囲白質軟化症(PVL)が提唱されて以降、脳性麻痺の治療や療育が中心だった時代を経て、超早産児の生存率が向上した近年では、後遺症として神経発達症に近い特性が見られることが注目されるようになりました。
このような疑問に向き合うため、2017年に「超早産児神経発達症研究会」を立ち上げ、研究を重ねてまいりました。超早産児(在胎28週未満)における神経発達の特徴は、正期産児に多い自閉スペクトラム症や注意欠如多動症とは異なり、診断基準を満たさないグレーゾーンの特性や、軽度の認知機能の低下が見られ、在胎週数が低いほどその傾向が強くなります。学童期以降には視覚認知の障害や学習困難、柔軟な対応の苦手さ、内向的な性格傾向が表れやすく、思春期以降にはうつ病などの精神的課題、さらに成人期以降の早期脳変性の可能性も指摘されるようになってきました。
しかし、超早産児に限らず、早産児(在胎37週未満)における多様な発達課題は、乳児期には気づかれにくく、明確な運動発達の遅れがない場合には早期療育へつながりにくいのが現状です。また、保育・教育現場での理解も十分とは言えず、医療においてもNICUフォローアップから発達に特化した領域や心身医療や精神科そして内科への円滑な移行支援体制は未だ整備途上にあります。
一方、研究分野においては、AI技術の進展とともに神経科学の分野でも新たな知見が得られ、脳の可塑性に注目が集まっています。胎児期からの予防的介入や脳保護戦略、さらには母親の心理的サポートや家族支援が、長期予後の改善に極めて重要であることが、科学的にも明らかになってきました。
本学会は、こうした状況を受けて設立された早産児の神経発達に特化した日本初の学際的な学会です。医療・教育・福祉・保護者支援といった多様な分野が連携し、早産児の生涯にわたる課題を多角的に捉え、これまでにない支援のあり方を共に模索してまいります。
早産児が幸せで健康な人生を送るためには、発達段階に応じた教育支援や、社会的理解の促進が欠かせません。出生時から発達的脆弱性を抱える早産児においては、年齢とともに課題のかたちが変化します。私たちは、神経発達に焦点を当て、脳機能の解明と臨床像の可視化を通じて、フォローアップ体制の整備と、本人・ご家族に寄り添った生涯にわたる多層的支援の構築を目指してまいります。
本学会の学術的・社会的な活動をより一層推進していくためにも、多くの皆さまのご参加と温かいご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
.png)